翼で飛行する砲弾
ロシア=ウクライナ戦争の発生にともなって、再び砲兵戦力に注目が集まるなか、アメリカでは新しい誘導砲弾「LRMP」が登場しました。日本語では長距離機動砲弾と呼び、「Long Range Maneuvering Projectile」の略称です。
アメリカは以前から砲弾の精密誘導化、長射程化に取り組み、前者はエクスカリバー砲弾、後者はロケット補助推進弾として存在します。
ところが、LRMPはGPS誘導とロケット推進を使わず、格納式の翼で滑空しながら、自身の捜索機能で目標に向かう仕組みです。
155mm榴弾砲から放ち、高度12〜14kmまで上がったあと、そこで翼を展開します。そして、高性能センサー、画像カメラで捕捉・追跡するため、GPSシステムが使えなくても、目標に対する精密攻撃が可能です。
この誘導機能にはMQ-9など、無人攻撃機の技術を流用しており、機械学習のアルゴリズムとともに、リアルタイムでの追跡を実現しました。
したがって、LRMPは目標に合わせて軌道修正を行い、おかげで固定目標に加えて、移動する目標(車両など)にも対応しました。
設計の工夫で長射程化
さて、LRMPは丸み帯びた三角形の形状を持ち、これが生産性の向上だけではなく、空気抵抗の軽減につながりました。先述の翼と組み合わせた結果、LRMPの最大射程は120kmまで伸び、長射程の精密誘導弾になりました。
この空気力学をふまえた設計を使い、LRMPはロケット推進を使わずとも、通常弾の約4倍の射程距離を誇り、遠方の敵を正確に叩きます。
長距離機動砲弾の名前のとおり、長い射程とGPSに頼らない誘導機能、途中で軌道修正できる柔軟性を確保したわけです。
その分のコスト増は避けられず、量産効果による変動はあれども、800万〜1,000万円になるでしょう。それでも、ミサイルを使うよりは全然安く、目標次第では十分な費用対効果を見込めます。
しかも、既存の榴弾砲で使える利点は大きく、海外への輸出を視野に入れると、さらなる量産効果を通して、コスト削減が期待できるかもしれません。
少なくとも、現場砲兵の選択肢は広がり、運用上の柔軟性が高まりました。ミサイルを使うほどでもない、でも従来型の砲弾では叩けない場合、そのギャップを埋める手段になります。
すでに米陸軍はテストを行い、GPSなしの状況下で「成功」しました。また、海軍向けの研究・開発も進み、射程を75kmに抑えながらも、127mm砲に対応した派生型が登場予定です。
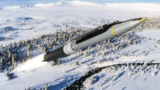




















コメント