本来は核燃料の護衛用
領海と排他的経済水域を合わせると、日本は世界6位の海洋面積を誇り、この広大な海の安全を守るべく、海上保安庁は24時間体制で警戒してきました。
むろん、海上自衛隊も日本の海を守り、一部の役割は海保と被るものの、事実上の軍隊である以上、彼らは最後の砦にあたります。一方、海保は平時の警察力を担い、日頃から海洋案件に対処する組織です。
そんな海保は370隻以上の巡視船・巡視艇を持ち、そのうち140隻は大型の巡視船として、長期間の外洋パトロールに投入されています。特に「しきしま」は船体規模が大きく、長年にわたって海保の象徴と評されてきました。
- 基本性能:巡視船「しきしま」
| 排水量 | 6,500t (基準) |
| 全 長 | 150m |
| 全 幅 | 16.5m |
| 乗 員 | 110名+航空要員30名 |
| 速 力 | 25ノット (時速46.3km) |
| 航続距離 | 最大2万浬 (37,000km) |
| 装 備 | 35mm連装機銃×2 20mmバルカン砲×2 |
| 艦載機 | AS 322ヘリ×2 |
| 価 格 | 約350億円 |
「しきしま」は1992年に就役した際、世界最大の巡視船として注目が集まり、海保にとってはまさに「虎の子」でした。その後、世界最大の座は中国海警局に譲り、徐々に話題にならなくなったものの、それでも「しきしま」は3番手の座を維持しました。
この「しきしま」は同型船がなく、異例の大型巡視船になったわけですが、なぜ建造されたのでしょうか?
その答えはプルトニウムの護衛です。
その少し説明すると、日本の原子力発電所では核燃料を使い、その使用済み燃料はイギリス、あるいはフランスの再処理工場に運びます。ここでプルトニウムと廃棄物に分けて、前者を再び日本に持ち込み、再利用する計画でした(プルサーマル発電)。
そして、海外から日本に核燃料を運ぶとき、当初は民間船に武装した海保職員が乗り、フランスとアメリカの軍艦が一部護衛を担いました。しかし、テロリストなどに奪取される可能性が否めず、アメリカが大きな懸念を示したことから、その対策として「しきしま」が建造されました。
このように核燃料の護衛と特殊任務を帯び、外洋航行に適した大型巡視船になったわけです。
重武装な巡視船として
核燃料の護衛を務めるべく、船の前後に35mm連装機銃、艦橋前に2基の20mmバルカン砲を置き、射撃指揮装置まで搭載しながら、遠隔操作ができるようになりました。
35mm機銃は550発/分、約5,000mの射程を誇り、連装式で火力強化を図ったところ、海賊やテロリスト相手には十分な威力を確保しました。
このように重武装な巡視船に仕上がり、その火力は従来型と比べものになりません。少なくとも、軍艦以外を相手するには申し分なく、本来の任務を果たせる能力を有しています。
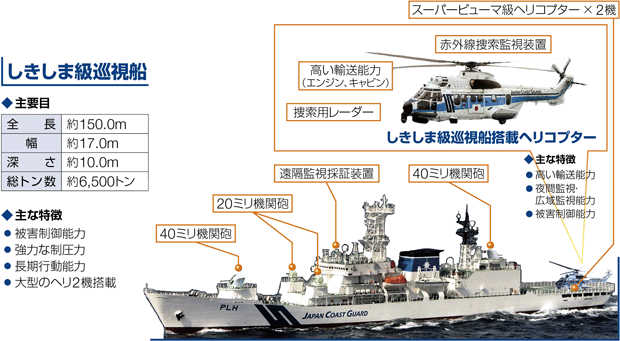 2番艦の「あきつしま」は40mm機関砲を搭載(出典:海上保安庁)
2番艦の「あきつしま」は40mm機関砲を搭載(出典:海上保安庁)
また、海自護衛艦の対空レーダーをふまえて、その改良型をあえて装備するなど、建造時は唯一無二の巡視船でした。
さらに、ヘリコプター×2を運用できるほか、全天候型の救難艇×2、警備艇×2を搭載しており、非常に高い救難能力を獲得しました。
外洋での長期航海を行うべく、船体構造は軍艦に準じた設計になり、艦橋の窓を含む外回りの多くが防弾仕様になりました。
そして、対テロを強く意識する関係から、「しきしま」は特に情報保全が厳しく、乗組員は数名の幹部を除き、ほとんど名簿には載っていません。
特殊任務を行う性質上、異例の重武装・秘密主義になった形ですが、実際に核燃料を護衛したのは「1回」にすぎず、それも就役直後の1992年11月でした。フランス出港時に環境活動家の船が近づき、体当たり攻撃を受けたものの、強固な船体構造のおかげで、任務には全く支障がありませんでした。
その後、プルサーマル計画が延々と進まず、2011年の福島原発事故でほぼ白紙化されたため、「しきしま」の出番は途絶えました。
 タンカー護衛中の「しきしま」(出典:海上保安庁)
タンカー護衛中の「しきしま」(出典:海上保安庁)
本来の役割を失ったとはいえ、その外洋航行力と航空運用能力は変わらず、遠方海域へのパトロールに加えて、東南アジアと太平洋諸国に派遣されてきました。
近年は中国海警局に対抗すべく、その延命改修も考えていたところ、就役から30年以上の船体は老朽化が激しく、最終的には2024年に退役しました。
思い入れがあるからか、その名前は「れいめい型」の4番船が受け継ぎ、2代目として鹿児島に配備予定です。





















コメント