自己完結を目指して
海に囲まれた日本の守りは、海上優勢の確保にかかっているなか、どんなに強い艦隊をそろえても、燃料がなければ意味がありません。
とりわけ長期作戦では補給艦が欠かせませんが、その補給艦が給油する燃料も、もともとは基地で受け取ったものです。さらに上流をたどれば、これら燃料施設・備蓄も民間製油所から運ばれてきた燃料を貯蔵しているに過ぎません。
つまり、製油所から基地への安定供給がなければ、海自艦艇は戦力を発揮できないのです。
ところが、「製油所→基地」における燃料輸送は民間委託しており、ここにある問題が潜んでいます。
こうした民間委託は経費削減などのメリットがあるとはいえ、自前で行うよりは時間がかかるケースが多く、海自向けの燃料輸送も発注から供給まで最大3ヶ月もかかってしまうそうです。
軍隊というのは自己完結を目指す組織であって、その生命線となる燃料についても、なるべく自前調達に近い形が好ましいでしょう(突き詰めれば、際限はないが)。
そこで、海自は初めての油槽船、いわゆるタンカーを建造することで、製油所から基地までの燃料輸送を自ら実施する体制をつくりました。
- 基本性能:油槽船「YOT-01」
| 排水量 | 4,900トン(基準) |
| 全 長 | 105m |
| 全 幅 | 16m |
| 乗 員 | 14名 |
| 燃料搭載量 | 6,000キロリットル |
| 価 格 | 1隻あたり約28.5億円 |
海自初のタンカーとなったのは「YOT-01」と呼ばれる船で、これは製油所で燃料を積み込んで基地まで届けたり、基地間の燃料輸送をするのが仕事です。
この油槽船は6つの燃料タンクを持ち、艦艇用の軽油やヘリ向けの航空燃料を約6,000キロリットル(600万リットル)も収容できます。
1キロリットルで護衛艦が40kmも進めるのを考えると、この6,000キロリットルというキャパシティがどれほど大きいか分かりますね。
 YOT-01の船員部屋はなんと個室(筆者撮影)
YOT-01の船員部屋はなんと個室(筆者撮影)
また、珍しいのが乗組員に「個室」を与えられている点です。通常、海自艦艇では艦長以外は個室をもらえず、このプライバシーのなさが人員確保の障壁になっていました。
個室化の試みは、油槽船の乗組員が14名しかいないからできるものですが、少なくとも現状改善には一石投じたといえるでしょう。
現時点ではYOT-01・YOT-02の2隻体制ですが、運用を通して評価されれば、その数は将来的に増えていくでしょう。
地味だが、頼もしい船
護衛艦に比べて地味ながら、こうした油槽船は「血液」ともいえる燃料を安定供給するには欠かせず、その配備は供給能力の自律につながるものです。
いままでも「油船」はたくさん持っていたものの、これは基地内の燃料施設から停泊中の船まで運ぶのが役割でした。一方、油槽船は燃料供給網のさらに上流(製油所→基地)も担えるため、民間への依存度が低くなり、運用における柔軟性を高められます。
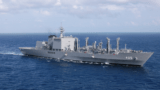




















コメント